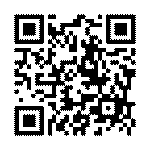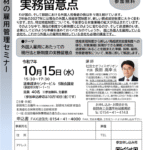道内の水産加工関連事業者に対して、生産性の向上や経営革新など、経営課題の解決に向けた取組みを支援するため、北海道中小企業総合支援センタースタッフや専門家派遣による集中的かつ継続的な伴走型支援を行います。
HACCP取得をはじめとした生産性の向上や経営革新など、経営課題の解決に向けた取組みを支援するため、北海道中小企業総合支援センタースタッフや専門家派遣による集中的かつ継続的な伴走型支援を行うものです。
事業の利用をご検討される際は、まず「経営健康診断問診票」をご提出いただき、その後、専門家の派遣が可能かなどを打ち合わせさせていただくこととなります。
当事業のWEBページ(こちらか問診票がダウンロードできます。)
支援対象者
次の各要件に合致する道内の中小企業者が対象となります。
〇道内に主たる事業所を有する中小企業支援法第2条に該当する中小企業者等であること。
〇水産品の加工、保管、輸送、販売および水産品の加工、保管、輸送、販売に要する機械設備、容器等の製造、販売(取付工事等を含む)等を行う水産加工関連事業者であること。
募集期間
令和5年4月17日(月)~令和6年1月末まで
※募集期間を変更する場合があります。また、応募が定数に達した場合は募集を終了します。
お申込方法
相談を希望する事業者は下段の「経営健康診断問診票」を提出願います。
※専門家の派遣が必要な場合は、別途「専門家派遣要請書」を提出していただきます。
費用負担
相談は無料です。
(専門家の派遣に要する謝金及び旅費は当センターが負担します。)
詳しくは下記URLでご確認ください。
https://www.hsc.or.jp/consul/suisanshien_r5/
(公財)北海道中小企業総合支援センター